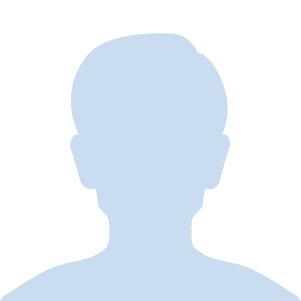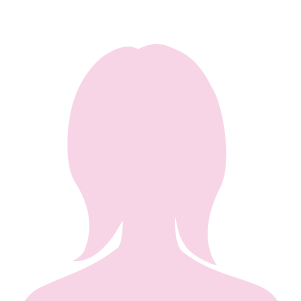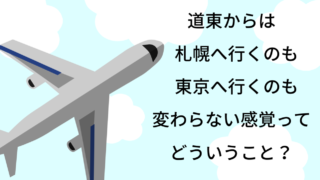北海道ツーリング好きが高じて、そのまま道東に移住し15年以上。バイク歴30年のなーしぃと申します。
今日はバイクのタンデムについてのお話を書かせていただきました。
私も二児の父親。かわいいお子さんと大好きなバイクに乗って、ぜひたくさんの思い出を作る参考にしてもらえると嬉しいです。

写真は40年以上前の私の姿…。親父もバイクも健在です。
これらの経験などを踏まえたお話です。よろしくお願いいたします。
・タンデムデビューは、子どもが3才のときでした
・「ヘルメット」「手袋」に加えて「タンデムベルト」「インカム」は特におすすめです
・子どもさんの成長に合わせ、バイクも乗り分けられると最高です
・同乗者も周りも、怖がらせないよう心掛けています
・「乗せる」ではなく「乗ってもらう」「趣味に付き合ってもらう」気持ちで
※私は父親ですので、文章中は「運転者はお父さん」表記がほとんどです。お母さんライダーの方、申し訳ありません。気を悪くせず読んでいただきますよう、お願いいたします。
子どもとタンデムツーリング、何歳から子どもを乗せてる?「私は3才からでした」

私の場合は、娘も息子も3才ごろには乗せて走っていました。
三輪車に乗るようになって「乗り物」に興味を持ち始めたころ。
お父ちゃんが休みの日に触っている「おもちゃ」に乗ってみるかい?という感じじゃなかったかなあ…と。

近くのお散歩ルートを、セカンドバイクだった「RV75」で走ったのが最初だったと記憶しています。
生まれてすぐから、バイクが身近な存在でしたので。またがって写真を撮ったり。
自然と慣れてくれていたように思います。
子どもとツーリングするのに、どんな装備が必要?「タンデムベルト、インカムは特におすすめ!」
ヘルメット

初めてのヘルメットは「妻のヘルメットにタオルを詰め込んで、形だけかぶってます」状態だったように思います。
最初はアライSZ-Light51-53センチ。子育て中の友人から譲っていただいたものでした。
保育園児には、ジャストサイズでした。

子も大きくなりサイズアウトを迎え、次はアライのSZ-Ram3 55-56センチ。
小学2年から6年生ごろまでかぶりました。買ってすぐは若干ほっぺたの部分に緩さがあったため、内装を換えサイズを合わせたように記憶しています。
子どもにはずっと「ジェットヘルメット」を選びました。子どもは視界が広いことを好みます。(狭いことを嫌がる、というほうが伝わりやすいでしょうか)
安全性云々の議論はもちろん承知していますが、やはり「イヤ」ということを排除してあげることが、今後継続して乗ってくれる要素として大きいのではないでしょうか。

私の子どもは年が4才離れており、ちょうどサイズアウトの時に「おさがり」となってくれたので、どのヘルメットも8年くらい使ってました。
(各メーカーさんが加入する日本ヘルメット工業会という団体では、耐用年数が3年なんて言ってます。そこのところは自己責任ってことで)
面倒とは思いますが、実店舗でサイズ合わせをしてみてください。
お好みのメーカーや色などがあるかと思いますが、子どもサイズって取り扱いが少ないため「あるものから選ぶ」くらいになってしまいますけどね。
「タンデムベルト」
タンデムライダーズさんの、その名も「タンデムツーリングベルト」というものを、かれこれ13年ほど使用していました。

 子どもをそのままリュックサックのように担いでしまおう、と考えていただければ良いでしょうか。
子どもをそのままリュックサックのように担いでしまおう、と考えていただければ良いでしょうか。
なかなか思いきった考えだな、と当時は思いましたがこの記事を書くにあたって検索してみると現在も現役の商品でした。完成されているのでしょうね。(アマゾンでは粗悪品っぽい模造品もたくさん売られています。)
商品説明には「居眠り」「脱落」「立ちゴケ」親子タンデム走行時の安心感をバックアップとあります。
適度な揺れと、単調なエンジン音がいいのでしょうか。
カクンっとなって持ち直しますが、またすぐ寝ます。

落ちられたら、冗談じゃ済まなくなりますからね。
 このベルト(ハーネスという表現の方がいいでしょうか)、頑丈です。安いものは分かりませんが、こちらの製品はベルト類が食い込まない太さがあり、縫製もしっかりと作られています。
このベルト(ハーネスという表現の方がいいでしょうか)、頑丈です。安いものは分かりませんが、こちらの製品はベルト類が食い込まない太さがあり、縫製もしっかりと作られています。
子どもの背中もしっかりホールドするように作られ、成長に合わせてベルトの長さを調整できるので、これまで寝ても脱落することはありませんでした。
モデルとなってくれた息子は、当時小学5年生でした。大きさも問題ありません。
 持つところ(グリップ)となる部分も付いてます。
持つところ(グリップ)となる部分も付いてます。
子どもが小さいうちは、バイクのグリップやシートのベルトに手は届きません。
よく考えられた品物でした。いいものを買ったと思っています。
ちなみに、妻も良く後ろで寝ます。ランチツーリング後なんかは即落ちです(笑)
おそらくベルトの位置を長くすれば、大人も装着可能かと思うくらい余裕はありますが実際に試したことはありません。寝落ちした大人を支えるほど、私自身が体幹は強くありませんので…

商品リンクを貼っておきますが、アマゾンではしょっちゅう売り切れています。(再入荷もしっかりあるようですが)楽天より、アマゾンの方が常に安く買えるようです。
2024.5現在で14093円と高価ではありますが、評価も高いです。お父さんお母さんライダーに人気商品のようですね。
手袋、長袖長ズボン

このあたりは通園や通学時に来ているジャンバーやジーンズ、スニーカーと軍手で十分かと思います。もちろん安全面で言えば革ジャン革パンツプロテクターなんでしょうけど、そんな物々しいことはしていません。
サイズも変わっていくので、お父さんのおこづかいでは持ちません(笑)

ただ、ワークマンで数百円で買った作業用の皮手袋はコスパ抜群で、子どもたちも「バイク専用の手袋」と喜んでくれました。これはよかったですよ。
ほどほどに大きくなれば、バイク専用品などで格好よくキメるのもおすすめ。やはり専用品って防寒防水などの点も含め、よく考えられて作られています。
インカム

「インカム必携」です。乗りながらコミュニケーションが取れる要素はとても大きいです。
走行中にも話が出来るっていうのは、本当に便利です。「右へまがりまーす」「左にまがりまーす」「とまりまーす」と合図の無いままバイクが動作をすると、後ろでびっくりするようです。コミュニケーションだけでなく、安全面を考えてもおすすめです。
バイク用品店行けばいっぱい並んでいますが、シェアの小さい日本仕様のものは私は敬遠です。
世界シェアで行けばAmazonで買うインカムがいちばん売れていて、そのぶん廉価。このあたりは「数多く売れている方が、ノウハウも多い」と思いますので購入者も多いLIXIN・B4FMをチョイスしました。
廉価品かもしれませんが、会話には何も困りません。以前使っていた有線式のものに比べると、わずらわしさが全くなく、大変便利です。
取り付けには内装を外したり、少々煩わしい感じはどうしてもあります。
しかしこれは、どのインカムを買っても同じこと。

付属品もしっかりしていますし、取り付け方法は親切な日本語のマニュアルも付属されていましたので心配はいらないかと思います。
評価もたいへん高く、もちろん私も価格や内容を考慮して5つ星のレビューをしました。
私は試す機会が無いのですが、他メーカーとのインカムとの接続も出来るようです。
どうせ買うなら、お子さんの分と2個セットが安く買えておすすめです。
※まれにセットで買うより、単品を2個買う方が安いときがあります。ご注意ください。
子どもとタンデムツーリング。おすすめのバイクって?「乗り分けができたら、最高です」
タンデムする対象で、バイクを変えてあげられるのが望ましいです。
子どもは「足つき性」を重視で考えてあげてほしいのです。ステップに足がつくと、運転している側も安心感が違います。
保育園児の頃は、どんなバイクでもステップに足がつかないです。しかし前述したタンデムベルトがあれば、運転者で体をサポートすることが出来るので、そう負担には感じません。

小学生くらいに成長し体も大きくなると、状況が変わってきます。
いくらタンデムベルトを用いても、足がステップに乗らないと同乗者も運転者も安定しなくなります。
そのため、同乗者が小さいうちは車体の小さい125cc程度の2種原付を準備してあげるのが最善ではないでしょうか。
近くの散歩から、片道100キロ程度の日帰りツーリング程度でしたら難なく走ってくれます。
都会に住む方なら、通勤最速号として準備されるのもいいのでは。

小学生の高学年くらいになると、2種原付では非力に感じるようになりますのでメインのバイクでのタンデムツーリングとなっていくでしょう。
大きめのシート。運転者も同乗者も、疲れにくいスタイルのものがいちばんです。
どうしても同乗者と荷物などの重さがアドバンテージとなるため、余裕のある排気量がほしいところ。同乗者の座り心地も違いますし、とっさのブレーキングにも余裕がもてます。

どの世代も「タンデムベルト」を装着しているのが前提です。運転者の体と、子どもさんの足つきの両方で、しっかりと保持してあげてください。
・変なカスタムはしない方が無難。
他に、カスタムしたバイクは後ろの同乗者には「迷惑この上ない」ことが多いので要注意。
マフラー交換はやかましいだけだし、思った以上に同乗者には騒音。マフラー交換のためステップ取り外しなんて乗りにくいだけでもってのほか。乗り心地を殺して見た目重視のカスタム車に乗せるのは、周りの見た目も良くないです。
子どもとタンデムツーリングをする際、どんなことに気を付けて乗っている?「同乗者も周りも、怖がらせないよう心がけてます」
バイク好きのお父さんライダーなら、一度は思うのですよ。「子ども乗っけて、走りたいなあ」って。
絶対です、絶対(笑)
お母さんライダーは、どうでしょうか。
その夢がかなうとき。うれしくなって格好よく見せたいものですが、周りはそんなこと何とも思っていませんから。
むしろ逆に「やめてほしい」と思われること・言われることが大半でしょう。
私は妻もバイクに理解があって、結婚前からタンデムツーリングに出かけていましたので「子どもをバイクに乗せる」ことに抵抗はさほどありませんでした。
しかし、やはり「バイクは危ない乗り物」であることは間違いありません。転倒や事故があれば「いきなりわが身」なのですから。

身内だけでなく「バイクは危ない乗り物」という考えの方は、思っている以上にたくさんおられます。
自分よがりではいけませんので、自身がバイクの乗り方を振り返り、常日頃から「理解してもらえるような運転」を心掛けたいですね。
タンデムでの運転自体に慣れていない運転者なら、なおさらです。バイクの挙動がまったく違います。いつにも増して安全運転でいきましょう。

さあ、乗るぞとなったら。
- 後ろの同乗者の、ヘルメットのあごひもをしめてあげて。インカムの準備はいいですか?
- 先に運転者がバイクにまたがって、同乗者がどうやってバイクにまたがるかを説明して。(大人だと左足を軸にガバッとまたがることもありますが、子どもだと車体左側のステップに左足を乗せて、運転者の両肩を支えにしながら乗ることになるでしょう。)
そのことを考えずに「はいどうぞ」状態にしていると、乗るときに見事にバランスを崩して運転者ともども立ちゴケ。格好よくなんて思いが吹っ飛ぶ大惨事になります。

バイクにまたがれないくらいの、小さな子どもを乗せる時はひと工夫を。
先に紹介したタンデムベルトを先に着けてもらってから、バイクの後部座席に先に乗せておきます。そのあとから運転者がバイクにまたがって、子が付けているタンデムベルトのハーネスを装着。子どもを背負いこむという形になります。
もちろん降りる時の手順も確認をしておきましょう。
事前に子どもに説明する項目としては
両手で持つ場所。(タンデムベルトのグリップ。大きくなってきたら、バイクのグリップも説明)
コーナーでは運転中にバランスを崩さないように、内側に体を倒したり外側に起こさないでほしいこと。(私子どもには背中を見ていてと説明していました。)
急ブレーキング時には手でつっぱらず、運転者に体を預けてほしいこと。
エンジンやマフラーが熱いときに触れないよう、分かりやすく説明を。
あまりいろいろ強制せず、かといって放置しすぎず。2度、3度と乗ってくれるようになると、何も言わず分かってくれるようになります。
あとは「今日はどこで何食べよう」とかそんなお話で。

事前に話はしなくてもいいですが「途中のトイレ休憩ポイント」は考えておいてくださいね。これ、結構重要な要素かもしれません。
特に子どもたちは「おしっこ!」とすぐきますから。運転者も余裕のあるコース建てをご検討ください。
子どもが嫌がらずに乗ってくれる秘訣は?「乗せるではなく、乗ってもらう」「タンデムツーリングに、付き合ってもらう」という感じで。
無理して乗せて出かけて、もうバイク乗らないなんてなるとおしまいですから。
無理しない距離からはじめて、雨の日乗らない。晴れた暖かい昼間限定といった感じで。
最初は徒歩でも数分の保育園まで、わざとバイクで行ったりして。
周りのお友達から「いいなあ」となるとうれしくなって。そこでわが子も「また乗せて」となって。
そうやって少しずつ、距離を伸ばして。夏の暑い日に、最寄りのコンビニまでアイスを食べによく行きました。

まあ、いいとこ小学校卒業の頃までです。親と一緒に出掛けるなんてことも。
タンデムツーリングは体調やその日の天候を十分考慮して、「お父さんのバイクの趣味に、子どもが付き合ってくれている」くらいの気持ちで、ちょうどいいと思いますよ。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の記事が、みなさまの参考としていただけたり、疑問解決の一助となりましたら幸いです。
今後とも北海道移住ブログ「なーしぃのひとりごと」をどうぞよろしくお願いいたします。